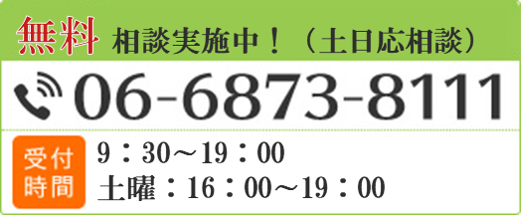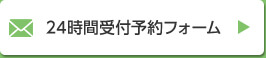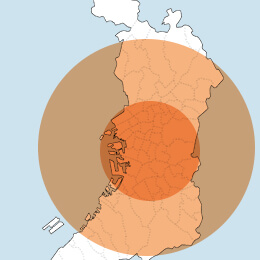被相続人が後妻に「全財産を相続させる」趣旨の遺言を残していたが、後妻に遺留分減殺請求をして、被相続人名義の口座から後妻が引き出していた使途不明金の95%以上を遺留分算定基礎財産に含めることを後妻に認めさせた上で、被相続人の子である依頼者2名が後妻からそれぞれ約290万円ずつ取得する内容で合意した事例
被相続人が後妻に「全財産を相続させる」趣旨の遺言を残していたが、後妻に遺留分減殺請求をして、被相続人名義の口座から後妻が引き出していた使途不明金の95%以上を遺留分算定基礎財産に含めることを後妻に認めさせた上で、被相続人の子である依頼者2名が後妻からそれぞれ約290万円ずつ取得する内容で合意した事例
依頼者 60代男性・50代女性(豊中市在住)
遺産 不動産・預貯金・保険
相手方 70代女性(兵庫県在住)
依頼の経緯
A(兄)・B(妹)さんの父親であるCさんが亡くなり、A・BさんとCさんの後妻であるDが相続人となりました。Cさんは「全財産をDに相続させる」旨の公正証書遺言を残しており、A・BさんはこのことをCさんの死亡後にDから突然伝えられました。また、公正証書遺言作成当時、Cさんは認知症を発症していた可能性がありました。A・Bさんは今後どのように対応すべきか分からなかったため、当方に相談に来られました。
弁護士がA・Bさんから事情を聞いたところ、「公正証書遺言作成当時、認知症によりCさんに意思能力がなかったことを窺わせる医師の診断書等の客観的な証拠はなく、主治医も分からず診断書の作成も依頼できない。」とのことでした。
弁護士が「Dが“Cさんの遺言は有効である”と主張してくることはほぼ間違いないので、遺言を無効とするためには、遺言作成当時Cさんに意思能力がなかったことをこちらで立証する必要があります。その客観的証拠がないとすると、遺言が無効であることを前提に遺産分割協議を成立させることは困難です。ただ、全財産をDに相続させる公正証書遺言があっても、遺留分減殺請求をすれば遺産の8分の1ずつをA・Bさんがそれぞれ取得することができます。」と説明したところ、A・Bさんは、Cさんの遺言の無効を主張することを断念し、当方に遺留分減殺請求を依頼されました。
事情
A・BさんはCさんが自宅不動産を所有していることは知っていましたが、不動産以外に預貯金等の財産をどれくらい有しているかは知りませんでした。
そこで、弁護士は、Dに対し、遺留分減殺請求をするとともに、預貯金を含むCさんの遺産の開示を求めました。
その結果、Dは、弁護士に依頼した上で、Cさんの預貯金等の遺産を開示してきました。
また、弁護士が、Cさんの預貯金口座がある可能性のある銀行名・支店名をA・Bさんから聞き取り、当該銀行にCさんの預貯金口座があるかどうか調査した結果、Dが開示してきた預貯金口座以外にCさんの預貯金口座はないことが分かりました。
その後、弁護士がCさんの預貯金口座の過去の取引履歴を取り寄せて確認したところ、Cさんが亡くなる約1年半前からCさんが亡くなった当日までに、Cさんの預貯金口座から合計約550万円(使途不明金)が引き出されている形跡がありました。
Cさんが亡くなる数年前には、Cさんは認知症がかなり進行して自分で預貯金を引き出せるような状態ではなかったため、この出金を行っていたのは当時Cさんと同居していたDであると考えられました。
上記使途不明金を含めると遺留分算定基礎財産が総額約2400万円(うち不動産査定額が約1390万円)になったため、弁護士は、Dに対し、遺留分相当額として、A・Bさんそれぞれに約300万円(遺留分算定基礎財産の1/8)ずつ支払うよう求めました。
これに対し、Dは「①DがCさんの預貯金口座から引き出した合計約550万円は、Cさんの生前の入院費・自宅の家電購入費・Cさんの葬儀費用等に充てられたものなので、遺留分算定基礎財産に含めるべきではない、②夫婦には扶養義務があるので、DがCさんの預貯金口座から引き出した合計約550万円は扶養義務の履行(婚姻費用)の範囲内であり、その意味でも遺留分算定基礎財産に含めるべきではない、③こちらで査定した不動産査定額は1270万円だったため、不動産の時価は1270万円と考えるべき。」と主張してきました。
その上でDは、「DがCさんの預貯金口座から引き出した550万円のうち、Cさんの葬儀費用約195万円を遺留分算定基礎財産から控除してもらえれば、残りの約355万円を遺留分算定基礎財産から控除しない内容で示談に応じる用意がある」と主張し、「DがA・Bさんにそれぞれ約260万円ずつ支払う」という示談案を提示してきました。
①について、遺留分額は、被相続人の遺産総額から生前債務を控除した金額を基に算定されます。葬儀費用は、被相続人が亡くなった後に支出されるものであり、被相続人の生前債務には当たりませんので、原則として遺留分算定基礎財産から控除されません。
また、約1年半という短期間に約550万円もの金額がCさんの入院費等のために必要になるとは考えられませんでした。
そこで弁護士は①について、「そもそも葬儀費用は遺留分基礎財産から控除されるべき債務ではないし、亡くなる前の1年半という短期間にCさんのために550万円もの高額な支出が必要になったとも考えられない。」とDに反論しました。
②について、弁護士がCさんの預貯金口座の取引履歴を確認したところ、約550万円の使途不明金の出金とは別に、毎月10万円程度を生活費(婚姻費用)としてDがCさんの預貯金口座から引き出している形跡がありました。
そこで弁護士は②について、「Dは婚姻費用として毎月10万円程度Cさんの預貯金口座から出金しており、婚姻費用として550万円引き出したとは考えられない。」とDに反論しました。
③については、A・Bさんは「早期解決できるのであれば、当方の査定額にこだわるつもりはない」との意向でした。
そこで弁護士は③について、当方の査定額とDの査定額の中間値である約1330万円を前提に遺留分額を算定し、「DがA・Bさんにそれぞれ約292万円ずつ支払う」という案をDに提示しました。
その後の交渉の結果、Dは、Cさんが使用する車いすを購入した際の13万5000円の領収書を提示した上で、「使途不明金の一部でこの車いすを購入しているので、使途不明金約550万円のうち、この13万5000円だけを遺留分算定基礎財産から控除してもらえれば示談に応じる。」と主張して、「A・Bさんに約290万円ずつ支払う」という示談案を提示してきました。
A・Bさんがこの案で合意することに納得されたため、最終的に「DがA・Bさんにそれぞれ約290万円ずつ支払う」という内容で合意しました。
投稿者プロフィール

- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
- 遺留分侵害額請求をされたが、葬儀費用等を控除して遺留分を算定することを相手方に認めさせて示談した事例
- 異母兄弟が主張してきた「依頼者の相続分を譲渡してもらう代わりに、依頼者に対して10万円を支払う」という案を撤回させ、「異母兄弟が遺産不動産を取得する代償金として、依頼者に対して130万円を支払う」という内容で遺産分割調停を成立させた事例
- 相続人である姉から遺留分減殺請求され、遺留分侵害額として約3000万円を請求されたが、依頼者が支払う金額を1900万円に減額させて合意した事例
- 被相続人が後妻に「全財産を相続させる」趣旨の遺言を残していたが、後妻に遺留分減殺請求をして、被相続人名義の口座から後妻が引き出していた使途不明金の95%以上を遺留分算定基礎財産に含めることを後妻に認めさせた上で、被相続人の子である依頼者2名が後妻からそれぞれ約290万円ずつ取得する内容で合意した事例
- 代襲相続人である被相続人の孫が遺産分割協議に非協力的であったが、被相続人の長女と妻から依頼を受け、長女は不動産以外の遺産の半額である約1000万円、妻は法定相続分以上の価値のある不動産を取得する内容で遺産分割協議を成立させた事例
- 不動産・預貯金の遺産分割協議を拒否する兄から1人1000万円(4人で総額4000万円)を取得し、遺産分割協議を成立させた事例
- 被相続人と面識のなかった半血兄弟(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)と交渉し、本来の相続分以下の金額で合意することを認めさせ、遺産分割協議を成立させた事例
- 被相続人の死亡から約4年半経過後に突然遺産分割調停を起こし、依頼者が被相続人の生前に同人の口座から出金した450万円を遺産に加えて計算すべきと主張する妹に対し、450万円の一部を被相続人のために使用したことを認めさせ、遺産分割調停を成立させた事例
- 突然遺産分割調停を起こし、遺産不動産の死亡後のリフォーム代等を遺産から支出すべきと主張する兄嫁に対し、リフォーム代は遺産から控除しないことを認めさせ、依頼者が代償金606万円を取得する内容で遺産分割調停を成立させた事例
- 「祖母の遺産を全て取得させろ。」と迫る叔母と交渉し、約1030万円を取得し、後日判明した遺産は依頼者が取得することにして、終局的解決を図った事例